土屋逵直ーー。
いや、土屋主税といったほうが世間の通りはよかろう。上総久留里藩2万石の嫡男として生まれ、ゆくゆくは藩主の座に座るべく厳しく育てられたと言う。だが、父の乱心が公儀の知るところとなり、彼の家は改易の憂き目にあった。それでも遠州周智郡に三千石をあてがわれ旗本として取り立てられている。よほど見込みのある人物であったのだろう。
屋敷は本所松坂町。茶の湯と連歌を嗜み、風流旗本として名が高い。とはいえ、彼の茶の湯も連歌も、決して、旗本御曹司にありがちな軽薄なものではない。「なかなかに巧み」と、彼の歌を評する声さえある。なるほど、確かにそうかもしれない。いかに三千石のお旗本とはいえ、そうでもなければ、芭門の十哲の筆頭とも呼ばれた宝井其角ほどの俳諧の達人が、彼の屋敷に出入りすることもなかろう。
元禄15年12月13日。その日も其角は茅場町の侘び住いから、本所松坂町の土屋主税屋敷へ向かう。道行きは東。筑波おろしに雪が混じり、風はあくまでも冷たい。
両国橋にさしかかったとき、向こう側から「ささやぁ 笹竹ぇ」と笹売りの声が聞こえてきた。年の瀬、大掃除の煤払いに使うため、笹がよく売れる。目に映る雪、耳に聞こえる笹売りの声……。其角が雅趣を感じたその瞬間、笹売りがふっと顔を隠すようなそぶりをした。もしやあれはーー。
「子葉殿!子葉殿ではありませぬか!」
其角には笹売りの顔に見覚えがあった。見覚えどころではない。かつて俳諧の道を手ほどきした、播州赤穂の藩士大高源吾ではないか。源吾の姿を見てとった其角は「子葉どの」と、かつての弟子を雅号で呼び止めたのだ。
源吾には、いまこうしてここを歩いていることを決して気取られてはならぬ事情があった。それ故、往来にかつての師の姿を認めたとき、顔を伏せたのだ。だが、こうまで大声で呼び止められたのなら仕方あるまい。
「これは、宝井殿。なにやら手前にかまけてご無沙汰を」
「お家の大事をお聞きしましてからこのかた、御身お案じ申し上げておりました」
「浪々の身とはいえ、この有様。誠にお恥ずかしい」
「いやいや。落魄が当たり前。決して、お恥なさることはない」
と、そのとき。ひきわ強い風が吹き付けた。二人が立ち止まったのは両国橋の上。川を渡る風の寒さはひとしおだ。半纏一つしか身にまとう物のない源吾の肌には刺すようでさえある。思わず源吾は、肩をすくめた。
「おお。その姿ではお寒かろう。」
其角は自分の羽織を脱ぎ、源吾の肩にかけてやる。そのまま戯れに其角はこう問いかけてみた。
「どうじゃな?昔ながらの風流の道、お忘れなくば、ここで一句お付き合い願いたい」
と、かつての弟子の顔を覗き込む。なるほど、未だに目は鋭い。俳諧の心を忘れた訳ではなさそうだ。
『年の瀬や。水の流れと人の身は』
ーー其角のこの発句を聞いたとき、源吾は唸った。いまこの刹那の二人の姿と、雪に埋もれる師走の両国橋の情景を見事に織り込んでいる。さすが我が師。とっさに出るような句ではない。しかし感嘆ばかりはして居れぬ。一刻も早くこの場をさらねばならない。そのためにはこの句をつがねばならぬ。源吾は息を飲みつつ言葉を繰った。
「……『明日またるる、その宝船』 では、これにて。御免くださりませ。」
と、脇句を継いだ後、源吾は足早に立ち去った。
『明日またるる、その宝船』。なんのことだろう?何か寓意があるのか。其角は首をひねりながら、土屋主税が屋敷への道中を急ぐ。本所松坂町についた頃には雪はさらに激しさを増していた。
「その、大高源吾なる浪人、確かに赤穂の浪士だな?」
其角から両国橋での出来事を聞かされた主税は改めて尋ねた。
「はい。浅野家お取り潰しの後、どこにも仕官せず、今は笹売りで活計を立てております。それにしても、『明日またるる、その宝船』とは不思議な脇句でございますよ。もし寓意があるとすれば……。あ!なるほど。わかり申した。どこかのご家中への仕官が決まったのでございましょう。それをそれとなく昔の師であるこの私めに伝えようと…」
「いや、違う」
其角の言葉を遮ってまで、主税はそう言い切った。
「そちには、武士の心底はわかるまい。明日は14日であったな。月こそ違えど亡き浅野内匠頭殿のご命日。そういえば明日、吉良家では茶会を催すという。……なるほど!そうか!あいわかった!!」
「土屋様、どうなさいました?」
「其角殿、明日もこの屋敷に参られよ。それも夜が良い。雪見酒としゃれこもう。我が家は吉良上野介が屋敷と塀一つの隣。面白いものが観れるやも知れんぞ……。」
元禄15年12月13日に本当にこんなことがあったのかどうか、知らない。だが、講談や浪曲でおなじみのこのエピソードが、たまらなく好きだ。忠臣蔵を観るたび、源吾の意地と、土屋主税の粋に感じ入って涙を流してしまう。
さて、元禄の頃の話ではなく、今日の話。
今朝の東京新聞は、一面に「『ニュース女子』問題 深く反省」という記事を載せた。記事は
本紙の長谷川幸洋論説副主幹が視界の東京MXテレビ「ニュース女子」一月二日放送分で、その内容が本紙のこれまでの報道姿勢及び社説の主張と異なることはまず明言しておかなくてはなりません
との記述ではじまる。
この記事だけを読めば、この書き出しはいささか面妖に映るのかもしれない。「社の姿勢」と「他局メディアで自社社員が行った言動」の乖離の言明など、本来、必要なかろう。許せぬというのであれば、即座に処分すればよく、言論の多様性なる価値に依拠するのならば捨て置けば良い話である。
だがこれは、本ブログをお読みになった方ならお分かりのように、先日、東京新聞に、佐藤優が寄稿したコラムへの「返答」と読めなくもない。
ここでも紹介したように、佐藤優氏は、東京新聞に寄稿したコラムの中で、「東京新聞は社論を明らかにすべきだ」と鋭く東京新聞を批判した。凡百の「長谷川があの番組の司会を務めていたことに言及せずに、『ニュース女子』を批判する東京新聞は卑怯だ!」という子供じみた批判のしようと、少し趣が違う。なぜ、佐藤氏がこのような言い回しで東京新聞を批判したのか、そしてなぜ、自社を直截に批判する佐藤氏のコラムを東京新聞がそのまま掲載したのか、その背景については、上記エントリーを参照していただくとして、ここでは改めて、「佐藤氏が東京新聞に『社論を明らかにせよ』と批判した」点に注目しておきたい。
これを踏まえれば、今朝の東京新聞の記事が「本紙のこれまでの報道姿勢及び社説の主張と異なることはまず明言しておかなくてはなりません」との書き出しで始まる意味が、分かるではないか。———つまり、東京新聞は、佐藤優氏の投げた「コール」に「レスポンス」したのだ。これで、コール&レスポンスが繋がった。ちょうど、源吾の脇句の寓意を、土屋主税がちゃんと読み解いたように。
東京新聞の記事では、「多くの叱咤の手紙を受け取りました」と、自社社員たる長谷川氏の関与に言及せずに、『ニュース女子』問題を批判する東京新聞の姿勢を批判する声が多数寄せられたことを示唆している。確かにそうだろう。佐藤氏のような粋な工夫をせずに、直截に東京新聞の姿勢を論詰する人は多いはずだ。
だがちょっと考えて欲しい。いかに新聞といえども客商売とはいえ、「顧客からのクレーム」に基づいて、にわかに、自社の社員の処遇なんぞ決めれるわけがない。「それじゃ、言論統制みたいなもんで、恐怖政治だ」と、これまた子供みたいなことを言いたいわけじゃない。「そんなに急いで、人事なんていじれない」と言いたいのだ。ましてや長谷川氏は、論説副主幹。一般企業で言えば、部長やヒラの取締役クラスだろう。そんなポジションの人物を、「顧客からクレームあったから」とただちに人事的に懲罰すれば、社内各方面に混乱が起こる。まず第一に、そのポジションに彼を上げてきた人事のメンツが潰れる。そしてキャリアパスが不明確になることで、現場の管理職に混乱が生じる。何よりも、この問題に一番槍をつけた現場の記者たちが「次は、顧客の声を根拠に『なんで長谷川のことを書かなかったのか』と叱られるんではないか」と萎縮する。と、考えると、ここは、急いで動いてはいけないところなのだ。ゆっくりゆっくり、軋轢が生じぬよう、組織にひびが入らぬよう、それでいて、きっちりと責任が明らかになるよう、体勢を整えなければいけない。それがマネジメントだ。
確かに、今日の東京新聞の記事では、長谷川氏の処遇をどうするのかについての言明がない。その意味では生ぬるいとの批判は成立しよう。だが、少し待とう。「とりわけ副主幹が出演していたことについては重く受け止めて、対処します」とまで書いてあるのだから。
こうなりゃもう、長谷川氏は、組織人として、外堀も内堀も埋められたも同然。組織側としては「あとは熟した柿が落ちるのを待つばかり」という状態だ。ここで、東京新聞に「ちゃんと処分しろよ!」「やるんなら早くやれよ!」と言い募るのは、ケツの青い証拠。大人なんだからさ。みんな、組織で仕事したことありゃわかるでしょ?だったら、もうちょっと待ってやろうや。
元禄15年の江戸の人士もそうであった。みな、待てなかったのだ。口さがない人たちは、「赤穂浪士はなぜ早く主君の仇を討たないんだ」「赤穂でのうて阿呆よ」とさえ罵ったという。
だが決して、赤穂の浪士たちはぐずぐずしていたわけではない。その間、大石内蔵助は、同志の結束を固め、脱落者が出るたびに面目の立つように脱落させてやり、一方で急進派を抑え込み、「吉良上野介の首を取る」という最終目標に向かって組織を固めていた。
大高源吾は、そんな大石のゆっくりとしたマネジメント手法に苛立ち、「大石殿の指図は受けぬ!」と暴発した江戸急進派に属する浪士だ。しかし、とある事件がきっかけで、大石の心底を悟り、その後は誰よりも大石への忠勤に励んだという。
雪の吹きすさぶ中、半纏一枚の姿で笹売りに身をやつし江戸の町を歩き回ったのも他ではない。吉良邸の様子を探るためだ。源吾は明日12月14日、吉良邸で茶会が催されるという情報をつかんだ。きっと吉良は屋敷にいるはず。その知らせを、愛宕下に潜伏する同志たちに一刻も早く知らせるため、両国橋を急いだのだ。その時、何の因果か、かつての師・其角とすれ違ってしまう。其角に「明日またるる その宝船」との脇句を残し、同志の元に源吾は急いだ。
元禄15年12月14日夜半。大石内蔵助以下播州赤穂浪士四十七名は、本所松坂町吉良上野介が屋敷に討ち入る。表門を破却し、塀にハシゴをかけ邸内に浪士たちがなだれ込んだ時、大石は源吾を呼び、隣家の土屋主税が屋敷への使いを命ずる。
「先の播州赤穂の城主、浅野内匠頭が家来、大高源吾」
と土屋主税の前に跪き名乗り上げる源吾の姿は、もちろん笹売りのそれではない。鎖帷子に身を固めた立派な武者振り。源吾は大石から命じられた口上を続ける
「筆頭家老大石内蔵助以下我ら同志四十七名、なき主君のご無念を晴らすべく、ただいま、ご当家隣家、吉良邸に推参仕りました。願わくば我らが忠義にご憐憫賜り、何卒この儀、お見逃し頂きますよう嘆願に罷り越しました次第」
主税は大きく頷くと、
「見上げたるお心がけ。吉良の家人、上杉の付け人、何人たりともこの塀乗り越えて我が屋敷に入るものあらば、不届き者として打ち捨ててくれよう。」と、応じる。
後ろで聞いていた其角はたまらない。そうか、これが子葉のいう「宝船」であったか。昨日の不思議な脇句の心底はここにあったか。なんたる不明。師として弟子に詫びねばならぬ。
「子葉どの!ようやくご貴殿の心底、わかり申した。ならば門出を祝っていま一句。『我夢と思えば軽ろし笠の雪』」
源吾にもう迷いはない。脇句はすぐに出来上がった
「『師の恩や たちまち砕く厚氷』 では、御免」
走り去る源吾の背中を見ながら、土屋主税は家臣に命じる。
「高張をもて!内匠頭殿のご家来衆を高張提灯で馳走せよ」と。
灯は吉良邸の庭を照らし出す。この灯があれば上野介を追跡することもたやすかろう。
ーーーいま、東京新聞が必要なのは、かわら版を読みながら「いつになったら赤穂の浪士は討ち入るのだ!」といきり立つ野暮天たちの群ではなかろう。もう少し待ってやろう。もう少し待って、東京新聞がどうやってけじめをつけるか見極めてやろうじゃないか。その道行で、もし東京新聞が苦しそうだったら、そっと高張提灯を掲げてやればいい。その光は、現場の心ある記者たちを照らすはずだ。みなで土屋主税になってやろうじゃないか。

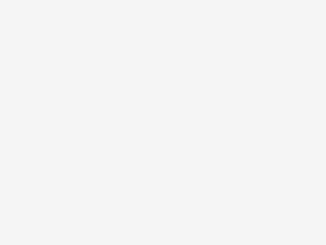
Be the first to comment